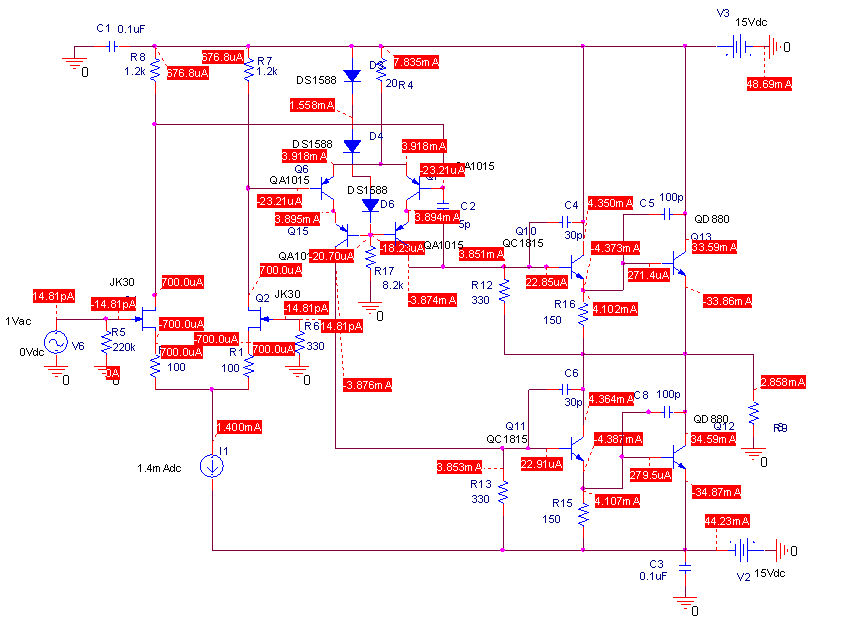
PSpice(評価版)で
電池式完全対称型パワーアンプをシミュレートする
我が電池式完全対称型パワーアンプのイメージである。
A607、C960、D188のモデルはないので、A1015、C1815、D880で代用する。このため、C1815のB−C間に30pF、D880のB−C間に100pFを外付けして多少なりともC960、D188に近付ける努力をする。
初段の定電流回路は電流源シンボルで代用し、初段カスコードアンプを省略してあるのは、全体でTRの数が10以内という評価版の制限があるためである。が、シミュレーション上問題はない。
各部の電流が表示されている。電池式だからどこも必要最低限だ。終段パワーTRのアイドリング電流も34mA程度で、結果全体で50mA程度のアイドリング時消費電流となっている。実際の我が電池式完全対称型パワーアンプもこれを50mAにセッティングしてある。
まず、8Ω負荷の場合のオープンゲイン電圧利得特性、位相特性を観る。
オープンゲインは低域で51.5db、高域での−3dbポイント(第1ポール)は75kHz程度である。
予想以上に広帯域だ。
この基本的要因はゲインが比較的小さいからである。
ゲインが小さいのは、パワートランジスタのアイドリング電流が34mAと小さいためだ。PSpice(評価版)はHfe−Ic特性もシミュレートしている、ということだろうか。
第1ポールは勿論2段目差動アンプの右側に入っているC=5pFによるものだが、終段パワートランジスタのベータ遮断周波数によるポールとの連星効果が生じてこうなっているものだ。
このアンプはクローズドゲインを26dbに設定しているが、オープンゲインが26dbになるポイントは1.5MHz付近でそのポイントでの位相遅れは−105°程度であるから、NFB後も安定に動作するであろうことが分かる。
位相補正を外して各部の電流ゲインを電流利得プローブで観る。
これでこのアンプの素性が殆ど明らかになる。
なお、ここではパワートランジスタに0.22Ωのエミッタ抵抗を付加してある。
グラフの下から、初段K30ドレインにおける電流利得(左右で10MHzまで一致し線が重なっている)、次が2段目A1015のカスコードアンプ出力点における電流利得(左右で20MHz弱まで一致し線が重なっている)、真ん中が終段のドライバーC1815のエミッタにおける電流利得(上下で10MHz超まで一致し線が重なっている)、上から2番目がパワートランジスタD880のエミッタにおける電流利得(上下で10MHz超まで一致し線が重なっている)、一番上がR18、すなわちアンプ出力点における電流利得だ。
一番下、初段の電流利得だが、−62.5dbである。ここでは入力に1Vacを加えているから出力が1Aであるとき、即ちgm=1Sのときが0dbである。従って−62.5db≒1/1335であるから、初段のgm=0.749mSである、ということになる。初段は差動の片側にしか入力がないので素子本来のgmの半分になるし、ソースに入った100Ωに電流帰還が掛かりその分gmが小さくなる。また、動作電流値が0.7mAともともと素子gmも小さい領域を使っていることもある。ということでgm=0.749mSと小さいのだ。従って電圧利得は2段目の入力インピーダンスが低いこともあり初段では減衰している、ということになるだろう。が、2段目へは電流で信号の伝達を行っているのでここでの電圧利得が減衰していることは別に問題ではない。
2段目までの電流利得は−24dbぐらいだろうか。−24db≒1/16であるから、2段目までの電流利得はgm=62.5mSである、ということになる。初段のgm=0.749mSであったから、2段目の電流利得は62.5/0.749=83.445倍ということになる。
ところで、2段目の電流ゲインは1MHz付近から減少し100MHz付近で初段電流ゲイン以下となってしまう。これは2段目A1015の素子としての高域限界であろう。A1015のfTは規格上>80MHzである。一番上の回路図からそのHfe≒177だからそのベータ遮断周波数は80/177=452kHzであり、その周波数領域からhfeが減少しft(トランジション周波数)の80MHzではhfe=1と素子としての増幅能力を失うのである。果たして・・・、グラフの線をよく見れば・・・400〜500kHzから電流利得が低下を始めている。まさにそうなっている。
真ん中が上下の終段ドライバーC1815のエミッタ出力点における電流利得である。低域で−12dbであるから≒1/4でgm=250mSということになる。2段目までで62.5mSであったから、終段ドライバーの電流利得は250/62.5=4倍ということになる。
小さい。のはエミッタ抵抗によって定常時はゲインが帰還に回っているからだ。が、これによって必要なとき(=パワーTRのHieが小さくなってベース電流増加を求めるとき)にドライバーとして必要な電流を供給できるのである。
さて、終段ドライバーのエミッタ出力点の電流利得は10kHz程度から上昇し800kHz付近でピーク(3db)となって、以降減少するという不思議なカーブを描く。
これは、次に述べるパワートランジスタの高域でのhieの低下に伴い、C1815がエミッタフォロア動作で帰還に回していた本来の素子ゲインをパワートランジスタの求め(hie低下)に応じてパワートランジスタのベース電流として供給するために増加し、1MHz付近からは2段目のA1015そしてC1815(fT>100MHz、hfe≒190)自身の高域限界による増幅能力の低下により電流が減少する、という事情によるものと考えられる。
上から2番目は上下の終段パワートランジスタD880のエミッタ出力点における電流利得だが、24dbである。よってgm=16Sである。ドライバーまでで250mS=0.25Sであったからパワートランジスタの電流利得は16/0.25=64倍である。
さて、これが100kHz程度から減少している。のは、パワートランジスタの高域限界だ。
M−NAO氏に教えて頂いたのだが、黒田某先生の「基礎Tr設計法」にこう書いてあるそうである。
「Tr内部のキャリアの蓄積はゆっくり立ち上がるので、1次遅れ要素を生み、これによるB−E間の(擬似的な)Cをベース拡散容量と言い、これとHieを含むベース・エミッタ間の抵抗とでLPFを形成する。これによるHfeのカットオフ周波数をfb(ベータ遮断周波数)といい、Hfeが1になる周波数をfT(トランジェンション周波数)という。低周波領域のHfeをβoとすると、fbが−3dbポイントで、以後−6dbで減衰し、fTでHfeが1となり、この関係は、fb×βo=fTとなる。」
D880は規格ではfT=3MHzだが、上の測定結果では3MHzではまだ終段TRに電流ゲインがあり、このグラフからは終段TrのfTは7MHz程度と読みとれる。電流利得の周波数特性からfb≒300kHzなので、計算上βo=23.3となるのだが、低周波でのHfeは一番上の回路図にある各部電流値から125と求められるのでどうも計算がイマイチ合わない。が、これは多分エミッタ抵抗による電流帰還(NFB)作用のせいだろう。これによってゲインは減少するが周波数特性は良くなる、というのはエミッタ接地動作では当たり前に見られる現象だ。
いずれ、このアンプにおいては、別途位相補正措置を講じない場合、終段パワートランジスタのベータ遮断周波数が最も低いポール=第1ポールを形成する、という点に間違いはないだろう。これは上のグラフの各部の電流利得の周波数特性から明らかだ。
今回は、この終段パワートランジスタのベータ遮断周波数を第1ポールとした電池式完全対称型パワーアンプで“広帯域No−139(もどき)”を考えるのである。何故か? それはトランジスタを終段に用いた完全対称型パワーアンプで広帯域化を狙う場合、このベータ遮断周波数が広帯域化の限界ポイントであるからだ。これを第1ポールとする以上の広帯域化は原理的に不可能だ。・・・と思う。(^^;
最後にアンプ出力点での電流利得は終段のPP動作により6db増加して30db≒32Sである。このアイドリング電流値であるとB級動作なので6dbゲインアップはしないはずと思えるのだが、このシミュレーションはそこまで細かくないのかもしれない。
ま、これでこのパワーアンプ全体でのGM=32Sであるから、負荷Rを出力に繋いだ場合のオープンゲインはA=32×R(Ω)となるはずだ。
そこで、この状態で8Ω負荷での電圧利得とその位相特性を観る。
電圧利得は32×8=256=48.16dbになるだろうか。
電圧利得は低域で48dbと計算どおりである。やはりパワーTRのエミッタに入れた抵抗でゲインが下がってしまうのだ。たったの0.22Ωで3dbもゲインが低下する。その分帰還に回り周波数特性的には良くなる訳だが、それは実はかまぼこの上の方をどんどん削って平らな面を広げているだけで、いわゆるGB積を改善するわけでもないので別に誇れることではない。のだが、昔も今もこれをやって自慢げな人も多い。<余談(^^;
ところで、No−139について、このエミッタ抵抗の有無やその銘柄で音が変わると言われるのは、このゲイン・周波数特性の変化も1つの要因となっているのだろう。
さて、その−3dbポイント(位相−45°)=第1ポールだが、250kHz程度となった。これは終段パワーTRのベータ遮断周波数によるものである。
問題はNFBを安定に掛けることが可能かどうか、であるが、クローズドゲイン26db設定を想定してオープンゲイン26dbのポイントを見ると2.5MHz付近である。このポイントでの位相遅れの状況が肝要な訳だが、残念ながら−140°となっており安全圏の−120°以内を超えている。したがって、このままでNFBを掛けると発振する可能性が高い。
したがって位相補正が必要になる訳だが、2段目の例の位置にCを入れたのでは勿論今回の主旨に合わない。
よって、初段にステップ型の位相補正を入れて、低域のポールを余り下げることなく1MHz超辺りの位相遅れをちょっと引き戻して位相余裕を確保する、という手法を採ることになる。
結果第1ポールの−3dbポイントの周波数が110kHz程度に下がってしまったが、ステップ位相補正の高域側の周波数=159/(0.56(kΩ)×0.00051(uF))=557kHz付近からの位相戻り効果も相まって、オープンゲイン26dbポイントの周波数1.3MHzにおける位相遅れが−105°と、位相余裕がNFB後も安全な範囲に改善された。
これならクローズドゲイン26dbで安定に動作するはずだ。オープンゲイン20dbのポイントでも位相遅れは−120°に収まっているので、クローズドゲイン20db設定も可能と思われる。
NFBを掛けてみよう。
クローズドゲイン26db。帰還後の位相特性は40kHzまではフラットである。
十分に安定動作するはずだ。
これで終段パワートランジスタのベータ遮断周波数を第1ポールとした完全対称型パワーアンプが作れそうである。
しかもオープンゲインでのfc=110kHzと広帯域である。
が、問題はGB積なので、オープンゲイン48dbでfc=110kHzといっても余りたいしたことではない。ということもあるし、今更パワートランジスタのエミッタ抵抗を入れるのもなんだかなぁ・・・という気がするのでそのエミッタ抵抗0.22Ωを取り去ってみた。
結果、fcは100kHzに下がった。が、オープンゲインは51.5dbと上がった。この状態で位相余裕も確保できている。
これで当初の2段目で位相補正した場合と同じゲインが確保され、かつfcは30kHz程度高域に上げることができた。
これなら従来の2段目の位相補正により第1ポールを確保する手法に変えて、終段パワートランジスターのベータ遮断周波数で第1ポールを確保するこの方式を試してみる価値もある。
という訳で、我が電池式完全対称型パワーアンプは早速改良されたのだった。
う〜ん、デリシァ〜ス!(^^)と、なかなか良さげな音が出た。
のだが、問題もあった。
出力オープンでは発振するのである。
負荷にスピーカー(要するに低い抵抗)を繋ぐと発振は止まるのだが、この場合でも実機では入力に入れているボリュームを動かすとアイドリング電流が増えだして発振しそうになる。こういう症状は発振一歩手前の状態だ。
音はとても良いのだが、これでは実用にはならない。
シミュレーションと実機が完全に一致するはずはない。こういうことは当たり前だ。
実機の方が終段パワーTrのfTが高いし、Hfeは小さいのでシミュレーションより周波数特性が良いのだろう、と楽天的(^^;に考えて対策を考える。
そこでこの対策だ。
出力にパラに0.1uF+10Ωを入れるである。
結果、高域の利得低下が早くなって位相余裕がさらに改善されたためだろう、入り口のボリュームをどう動かそうとアイドリングが変動するなどという発振直前の不安定さは全くなくなった。
が、−3dbとなる第1ポール、fcも80kHz程度に下がってしまった・・・。これでは何のためにこうしたか分からない(爆)
ま、いいか。(^^;
と、落ちが付いてしまったが、さらにいくつかのテーマのシミュレーション。
まず、2段目で位相補正した場合、出力にパラの0.1uF+10Ωがなくても出力オープンで発振しないのは何故か? 逆に終段ベータ遮断周波数を第1ポールとした場合には何故これが必要なのか?
最初に2段目で位相補正した場合。
出力の8Ωを取り去ってオープンゲインでの電圧利得特性と位相特性を観る。
まさに連星効果!! といったところだ。
低域でのオープンゲインは91dbにも達している。
fcも当然1.1kHz程度に下がっているが、凄いのはそこからの利得低下が3MHzまで6db/octの直線であることだ。
そして、終段の100KHzのポールは完全に隠れ、かえって連星効果の位相戻し効果で位相遅れ−90°の範囲が1MHzまで続き、位相遅れ−120°のポイントは4MHzだ。
結果、ゲイン26dbのポイントでの位相遅れは−105°だから、これで安定なのは当たり前だ。
2段目で位相補正した場合は威力絶大な連星効果が働く。故に、出力にパラに0.1uF+10Ωを繋いでおく必要などない、ということなのだ。
では、その2段目の位相補正を止めた場合はどうなるのか。
果たして・・・この場合は第1ポールによるfcは7kHz程度になるが、このfcを形成している要素は何なのか? は、次に考えることにして、取りあえず電圧利得特性と位相特性からすると、こちらは2段目で位相補正した場合に比して位相の回転が速いことが分かる。
オープンゲイン26dbのポイントでは位相遅れが−120°を超えている。
といっても−120°をやや超えた程度だから発振には至らないかも知れない。
が、できればもう少し位相余裕を稼いだ方がよいだろう。
そこで初段のステップ型位相補正。という訳だが、その効果はどうか。
う〜ん、実に上手い!(^^)
ステップ高域側が300kHz〜3MHzでなんとも上手く位相の戻し効果を発揮してくれるものだ。
が、残念なことに、ステップ低域側の位相回転の影響で全体的にやや位相回転が早まってしまったために、位相の戻し効果が働く周波数で既に位相が−120°を超えてしまっている。このため、オープンゲイン26dbポイントでの位相回転は逆に−140°と進んでしまった。
これではNFBを掛けると発振する。
実際、我が実機でもこの状態では出力オープンで発振した。
そこでさらに出力に0.1uF+10Ωをパラに入れる訳だが・・・
何と、これがまたステップ型位相補正として利いた・・・ということだろうか。
fcは1.5kHzに下がってしまったが、このためにオープンゲイン26dbポイントが1.5MHz付近に下がるとともに、10kHz付近から位相戻し効果が現れて高域での位相回転が遅れるために、そのポイントでの位相遅れが−115°と安全圏に収まった。
これならNFB後も安定動作することになる。実際、我が実機でもこの状態で出力オープンでも安定だ。
さて、0.1uF+10Ωを切り離して、今度はこの場合に出力オープン時にfcを決定している要素は何か?という問題だが、オープンゲインが91dbという巨大なものになることによって終段ドライバーのCobが利いてきた可能性があるような気がする。
そこで、パラメトリック解析でC4,C6を3pF、8pF、18pF、38pF、78pFと変化させて観てみる。C1815の規格上のCob=2pFと合わせてCobが、5pF、10pF、20pF、40pF、80pFと増えていった場合というイメージだ。
やはり利いていることは間違いなさそうだ。
終段ドライバーのCobは、終段パワーTR自体の電圧ゲインをAとしてミラー効果により1+A倍に拡大される。
問題はAであるが、これは 32(S)×R(Ω)/62.5(mS)×0.33(kΩ)で求められる。330Ωは本当は終段ドライバーTRの入力インピーダンスがパラで利くので厳密にはもっと低いのだが、これは150Ω×hfe+hieなので無視して構わない数値だ。ので、無視する。(←おっと、間違った。(150Ω//パワーTRのhie)×hfe+hie なので無視できる数値ではないですね(^^;。でもまぁ→)ここはアバウトで良い。
これで概算すると、
負荷 A ポール(Cob30pFとして)
4Ω 6.2 2.6MHz
8Ω 12.4 1.3MHz
16Ω 24.8 623kHz
32Ω 49.6 302kHz
64Ω 99.3 160kHz
300Ω 465.5 34.4kHz
1200Ω 1861.8 8.6kHz
普通のスピーカーを負荷にしている限りはドライブTRのCobによるポールが主役に躍り出てくるということはなさそうだが、負荷が100Ω程度以上ではドライブTRのCobによるポールが第1ポールの地位に就くことが分かる。
したがって、この状態は利いているというレベルではなくて、ドライブTRのCobがミラー効果で拡大され、これと330Ωとで形成される時定数が第1ポールになっているのだ。
この状態は終段上下のパワートランジスタ同士が相互にいわゆるアクティブロードになっている状態だが、以上の計算及びfcの状況からして、終段パワートランジスタのそもそもの出力インピーダンスは1kΩ超程度ではないか、とこの結果から推測されることになる。
では、それほどにゲインが高まっていれば終段パワートランジスタ自体のCobも利いてくるのではないだろうか?
パラメトリック解析でC5,C8を1pF、70pF、210pF、490pFと変化させて観てみる。
D880の規格上のCob=70pFと合わせてCobが、71pF、140pF、280pF、560pFと増えていった場合というイメージだ。
なるほど。
低域に影響なしということではないが、これは低域にある別の時定数が高域での時定数の変化を連星効果で受けているもので、パワーTRのCobによる時定数が低域に現れたものではない。
終段パワートランジスタのCobによる時定数はこれが数百pFでもMHzオーダーなのだ。それはドライブインピーダンスが非常に低いからなのであろう。終段パワートランジスターのCobはあまり気にする必要はない、ということなのだ。
それよりもベータ遮断周波数の方がよほど重大な訳だ。
パワートランジスタのCobはそれほど神経質になる必要がないことは分かったが、その前には終段ドライバーのCobの影響は大きいことが分かった。
ま、負荷が普通のスピーカーであれば問題ないようだが、もう一度、パラメトリック解析でC4,C6を3pF、8pF、18pF、38pF、78pFと変化させて観てみよう。
勿論、C1815の規格上のCob=2pFと合わせてCobが、5pF、10pF、20pF、40pF、80pFと増えていった場合というイメージだ。
負荷は8Ωである。
やはり、負荷に8Ωが繋がった実働状態では、オープンゲインが低域で52db程度と大幅に低下することもあって、ドライバーのCobによる時定数はMhz以上の高域に移動し、その低域への影響は微少なものだ。第1ポールのパワートランジスタのベータ遮断周波数によるポールに高域から連星効果としての影響を与えているだけである、ということが分かる。
ドライバーTRのCobも神経質になる必要はないのだ。
が、我が“電池式完全対称型パワーアンプ”は、実は“ヘッドフォンも鳴る”というぐらいでヘッドフォン接続も予定しているのである。それもインピーダンス300Ωなどという外国産ヘッドフォンを繋いだりするのである。
となると、ドライバーTRのCobによるポールが地上に降りて来そうだ。
最後に、アンプ最終状態で出力に繋がる負荷を4Ω、8Ω、16Ω、32Ω、そして300Ωと変化させてその場合の電圧利得、位相の特性変化を観ておきたい。
位相特性は上から4Ω、8Ω、16Ω、32Ω、300Ωの場合である。電圧利得特性は逆に上から300Ω、32Ω、16Ω、8Ω、4Ωの場合だ。
電圧利得は負荷抵抗に比例して6dbステップで増加する。
4Ωから32Ωまでは、終段ドライバーのCobによるポールは、パワートランジスタのベータ遮断周波数による第1ポールより高域に位置しているはずである。
が、負荷300Ωではfcが20数kHzとなっており、この場合はもうドライバーのCobによるポールが終段のベータ遮断周波数によるポールの位置を超えて低域側に移動して第1ポールの地位に就いている、ということになる。
いずれの場合においても連星効果が働いて、まるでワンポールしか存在していないような特性図だ。が、電圧利得特性図が高域まで平行を保ちながら減衰していく、というところはまさに連星効果である。
これで、我が電池式完全対称型パワーアンプにあっては、スピーカーで聴く場合とヘッドフォンで聴く場合ではメインポールが交代してしまう、ということになるのだが、はたして音も微妙に違うものになっているのだろうか?
確かに、スピーカーで聴くときは終段D188の音がし、ヘッドフォンで聴くときにはドライバーC960の音がする・・・?(^^;<駄耳
(おまけの未来予想図)
オープンゲイン51.5dbではfo=80kHzでもやはり物足りない・・・。という不満に勝てなくなったときにはこうしよう。
パワートランジスタのベータ遮断周波数による第1ポールをやや引き上げるためにエミッタ抵抗0.22Ωを入れる。
これによるオープンゲインの低下を埋め、さらにゲインアップを図るために初段にgmの大きいK117を起用する。
初段の電流値を変えたり、初段の負荷抵抗値を変えたりすると、実機では温度補償の設定まで計算し直して変更しなければならなくなるので、他は変更しない。
が、これだけの変更で高電圧を初段に掛ける必要もなく、2電源のままで、よりハイゲイン・ワイドレンジな電池式完全対称型パワーアンプになるだろう。
fo=80kHzのままで良いのであればエミッタ抵抗0.22Ωは入れなくて良い。その場合はオープンゲインをさらに余計に稼げるはずだ。
オープンゲイン57.5db、第1ポールfc=90kHzが得られる。
十分ではないか。
2段目のゲインを生かしたこと、これがこの構成でこの結果を可能にしたのである。
で、未来はいつか?
う〜ん、以上は結局シミュレーションでしかないし、現実にそうなるかどうかを確かめるすべを持っていないし・・・
ま、気分次第ですかね(^^;
(2003年2月9日)